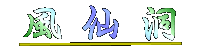古代日本と分水界
最終更新:2024/11/23
作成:2024/01/24
私は中学生の頃から地図を見るのが好きである。父も祖父も好きだったし、最年少の叔父は大学の地理学科卒業だから、環境的な遺伝なのだろう。そんな私なので、Google マップの地形表示や Google Earth を見て、河川を利用した古代の交通路を夢想してしまった。
1.黒井川(由良川水系土師川支流)
~高谷川(加古川水系柏原川支流)
標高約 95m と、本州一低い分水界として有名で、『石生の水分れ』(いそうのみわかれ)という名前が付いている。日本一と思われた時期もあった(日本一低い分水界は北海道の千歳空港付近)。水分れ公園のそばには「氷上回廊水分れフィールドミュージアム」という資料館までできている。
- クリックすると別ウィンドウで Google マップが起動
黒井川は、土師川経由で由良川に繋がり、福知山市経由真鶴市で日本海に注ぐ。高谷川はすぐに柏原川に合流し、西脇市・加東市、加古川市で瀬戸内海に注ぐ。
2.円山川~市川
兵庫県朝来市生野にも分水界がある。余談だが、少し東には生野銀山がある。
- クリックすると別ウィンドウで Google マップが起動
北流する円山川は、養父市・豊岡市経由、城崎町で日本海に注ぐ。南流する市川は、そのまま姫路市で瀬戸内海に注ぐ。姫路市にも古墳が多い。
3.上下川(江の川水系)~
矢多田川(芦田川水系)
府中市の「上下」という冗談のような名前の地区を流れる上下川は、北西に流れて田総川に合流し、三次市中心部のある三次盆地で南からの江の川と合流、やがて江津市で日本海に注ぐ。中国地方の分水界がこんなに南に寄っていることは驚きである。南方向には矢多田川が流れ、芦田川に合流して府中市を経由し、福山市で瀬戸内海に注ぐ。
- クリックすると別ウィンドウで Google マップが起動
近代化以前の江の川は、中国地方最大の河川として中国地方の交通の大動脈であった。古墳時代の三次盆地には特異な四隅突出型古墳が築かれた。江の川の「ゴウ」の語源は不明なので、私は魏志倭人伝の「狗奴国」と関連があるのではないかと夢想している(→「狗奴国=江の川流域『江の国』説」のページへ)。
4.簸川(江の川水系)
~根谷川(太田川水系)
日本海と瀬戸内海を繫ぐルートのひとつとして、日本海側江の川(ごうのかわ)水系と、瀬戸内海側太田川水系を結ぶ線がある。分水嶺は江の川支流の可愛川(えのかわ)の更に支流である簸川(ひのかわ)の水源は、安芸高田市と広島市安佐北区の境で、太田川支流の根谷川(ねのたにがわ)の本流と支流の入甲川がすぐ南側を流れている。
- クリックすると別ウィンドウで Google マップが起動
地図で見ると、赤いマーカーの北東側は、水源とは思えないようななだらかな土地であって、実際 Google マップの衛星写真表示ではメガソーラーらしき建物が建っている。遙かな昔、中国山地が今ほど隆起していない頃、入甲川の水は北の可愛川側に流れていたそうである。
➥ 外部サイト:「広島県:上根峠,根谷川と簸川の河川争奪」
5.彦山川(遠賀川水系)~今川
福岡県の北部を占める直方平野には九州有数の遠賀川が流れる。遠賀川の本流は西部の飯塚市・嘉麻市方面を源流とするが、東部の中央を大きな支流である彦山川が流れる。田川市あたりでは、東からの金辺川(きべがわ)、中央部の彦山川、西の中元寺川の3本となっている。金辺川のさらに支流が御祓川で、赤村立赤中学校のあたりが行橋市で瀬戸内海に注ぐ今川との分水界である。彦山川と今川の分水界でもある。
- クリックすると別ウィンドウで Google マップが起動
遠賀川式土器で有名な遠賀川流域であるが、古墳は支流の彦山川沿いに並ぶ。平成筑豊電鉄内田駅のすぐ北西には、巨大前方後円墳ではないかと取り沙汰されている地形がある。実は私は、河川交通の要所である赤村、大任町、田川市あたりが魏志倭人伝の為吾国だと推定している。「魏志倭人伝の国々2」のページ
6.筑後川~大分川
最後は九州最大の河川である筑後川と由布市を経由し、大分市で瀬戸内海に注ぐ大分川である。分水界はご丁寧にも「水分峠(みずわけとうげ)」と名付けられている。
- クリックすると別ウィンドウで Google マップが起動
水分峠の西にある日田市は九州の軍事的要衝で、九州は日田方面から攻められると陥落しやすいらしい。筑後川が平野部に出る三角州に「うきは市」があるが、元の漢字である「浮羽」からは東国へ抜ける関所である「不破関(ふわのせき)」が連想される。
また、日田市日高町にあったダンワラ古墳からは「金銀錯嵌珠龍文鉄鏡(きんぎん さくがん りゅうもん てっきょう)」というとんでもない代物が出土している。あの三国志の曹操自身の持ち物と同型式である。